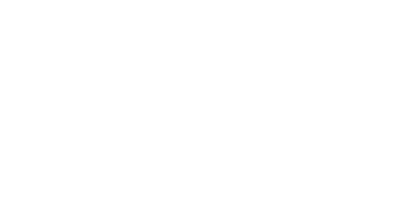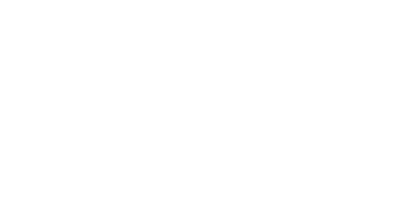
2021.12.25
ずっと、クリスマスが嫌いだった。
クリスマスに浮かれる人々を見るのも嫌だった。
本当に幼い子どもの頃は楽しみだったその日が、そう変わったきっかけをエレンははっきり覚えている。彼が6歳、リヴァイが21歳。出会って初めての年の冬だった。
「リヴァイさん! クリスマスの日の夜、オレんち来てくれる? クリスマス会やるから」
いつものように大学から帰る時間を狙い、市立図書館の前で待ち伏せしていたエレンに、興奮した笑顔で手作りのカードを渡された。約束しているわけではなくとも、エレンが毎日のようにそこで彼を待っていることに、もはや驚くことはない。日が落ちるのが早くなったから、できるだけ早く行ってやらなくてはと思いながら帰路についたリヴァイは、鼻の頭を赤くして笑う少年の姿に思わず頬が緩む。
「クリスマス会か」
リヴァイは手渡された画用紙を開く。拙い字で「12月25日 しょうたいじょう」と書かれたそのカードらしきものには、切り絵のクリスマスツリーが貼ってあった。
「ご招待ありがとうな。必ず行く」
へへ、と照れ笑いをしたエレンは、するりとリヴァイの手の中に自分のてのひらを滑り込ませた。その手は真っ赤になって冷えている。
「お前、今日は手袋どうした」
「……落としちゃった、片方」
またか。リヴァイは苦笑して、買っても買っても何度でも落としてくるのよ、あの子、とプンプンしていたカルラを思い出す。
「出かけるたびにちゃんと着けていれば落とさないだろう。なんで着けてないんだ」
「だって、母さんが買ってくるやつ、変なんだもん」
生意気な口調でエレンは言う。その顔に「リヴァイさんはわかってくれるよね?」と期待が見え隠れする。リヴァイは思わず吹き出し、「変とは言わないけどな」と控えめに同意をした。カルラがエレンに買い与えていた手袋は、大きく車の絵が書いてあったり、くまの柄が編み込まれていたり、つまるところすこし子どもっぽいのだ。リヴァイはそれを微笑ましく思うが、当の本人としては納得いかないのだろう。
「ほら、これ貸してやる」
リヴァイは自分がはめていた手袋をとって、エレンに渡した。彼は喜んで自分の手には大きな「大人の手袋」をはめ、ご機嫌な様子を見せたが、すぐに片方をとってリヴァイの手に押し付けた。
「リヴァイさんの手が冷たくなっちゃう。一個でいい、オレ」
そうしてまたするりとリヴァイの手をとり、にっと笑った。
「こうやって片方ずつはめて、着けてない手はこうやって繋げばいいんじゃない? ほら、ふたりともあったかい」
世紀の大発見をしたかのように得意げに言うエレンがかわいくて、リヴァイはにこにこ顔で寒空の下を歩くその頭を空いた手でぽんぽん撫でる。そしてその繋いだ手を自分のコートのポケットに入れた。手袋に守られていたリヴァイの指先の熱が、エレンに移ってポケットの中でほかほかと温まっていく。
「こうすれば、もっとあったかいな」
「リヴァイさん、頭いい」
「……そうか」
子どもの、子どもらしい素直な称賛に思わず笑う。そうして、招待されたクリスマス会には手袋を送ってやろうと思いついた。エレンが気に入って大事にするような、すこし大人びたデザインのものを。
そうして迎えたクリスマス会の日、小さな包みを抱えてリヴァイはイェーガー家を訪れた。部屋の中にはエレンとカルラが飾りつけたという大きなクリスマスツリーが鎮座し、テーブルの上にはすでに丸々一匹の鶏を中心に豪華な食べものが並んでいる。リヴァイは呆気にとられ、今も忙しなく料理を用意し並べ続けるカルラに詫びた。
「すみません、……こんな豪華な……、家族の団欒にお邪魔してしまって」
「あら、いいのよ! エレンがどうしてもリヴァイくんを呼びたいって言い張るの。リヴァイくんが一緒じゃないとつまらないんですって」
せっかくのクリスマスだからね、とエレンがなぜか得意げに言った。
事件が起こったのは、食後にみんなで大きなホールケーキを食べていた時のことだった。リヴァイのポケットの中で携帯電話が震え出し、「すみません」と一言置いて、リヴァイは部屋の隅でその電話をとった。短い会話をしてから電話を切ると、待ち構えていたようにエレンが尋ねた。
「リヴァイさん、誰?」
詮索するんじゃないの、とカルラに頭をはたかれる。
「母親だ。誕生日おめでとうと、クリスマスおめでとうってな」
「えっ、リヴァイくん今日お誕生日なの!? おめでとう!」
カルラとグリシャが朗らかに言い、「ケーキもう一切れ食べる?」「先に言ってくれてたらねぇ」「ありがとうございます」と和やかに流れていた空気の中だった。エレンがカシャン、と持っていたフォークを落とした。
「エレン?」
何してんのよ、とカルラがフォークを拾い上げるのも構わず、エレンは真っ青な顔で、目を見開いてリヴァイを見つめる。
「リヴァイさん……、今日、……お誕生日なの?」
「……そうだ。……おい、それがどうした」
途端にエレンはぶわっと目に涙を浮かべ、それを恥ずかしげもなくぼたぼたとこぼし始めた。ギョッとしてリヴァイがカルラの顔を見ると、夫妻も驚いて顔を見合わせている。
「おい、エレン、何がどうした」
「……知らなかった……」
嗚咽まで始めたエレンが、ガタンと立ち上がって二階へ駆け上がっていく。その後ろ姿を慌てて追いかけ、リヴァイはエレンの自室に足を踏み入れた。
「何なんだ……」
ベッドに突っ伏して泣くエレンのそばに腰掛け、その頭をやさしく撫でる。今年から与えられたというエレンの個室には、真新しい学習机やランドセル、壁に貼られた時間割や転がったえんぴつなど、遥か昔の記憶を呼び覚ますようなものたちが並んでいる。机の上に敷かれた塩化ビニルのデスクマットの下には、ふたりで撮った写真が差し込まれていて、リヴァイは苦笑した。それは今年の秋、リヴァイがエレンの作品を見に小学校の展覧会へ行った時の写真で、展示されていたのは夏休みの思い出としてエレンが「リヴァイさんと虫とり」を水彩絵の具で描いたものだった。そのことを知らされていなかったリヴァイは、画用紙に描かれた自分の姿に大層驚いたのだ。
「……なんで、わらってるの」
ぐすぐすと枕の下から声が聞こえ、リヴァイは楽しそうに言った。
「お前、オレと一緒に撮った写真あんなとこ入れてんのか」
「……そのリヴァイさん、かっこいいから、好きなんだもん」
そうか。直球なエレンの言葉に虚を衝かれ、間の抜けた返事をしてしまう。かっこいい? リヴァイの目には、乏しい表情でエレンの隣に立ついつも通りの自分の姿しか見えない。
「そんなことよりお前、何でいきなり泣いたんだ」
すこし落ち着いたらしいエレンが身体を起こしたので、下から覗き込むようにしてリヴァイは尋ねる。エレンの目にまた涙が溜まり始めたので、慌てて「何かしたか、オレが」と重ねて問いかけた。エレンは嗚咽を抑える努力をしながら、絞り出すような声で言った。
「今日、リヴァイさんの……お、お誕生日なら、お誕生日会にすればよかった」
「……は?」
「リヴァイさんのお誕生日なら、リヴァイさんのお誕生日だけにしたかったのに……オレ、リヴァイさんにプレゼント、ない」
「さっきくれたじゃねぇか」
先ほどエレンは、リヴァイに貯めたお小遣いで買ったというハンカチを贈ってくれたのだった。小学生になったから毎月お小遣いがもらってんだ、と誇らしげに言いながら。
「あれは、クリスマスプレゼントだもん……」
「同じことだろう」
「全然違う!」
またうわぁんと大きな声を出し、エレンは泣き始めた。
──お誕生日は、その人だけの特別な日なはずなのに。その人だけが、特別に扱われて、お祝いされるべき日なのに。その人のためにお祝いの準備をして、ケーキを買って、プレゼントを用意する。その人の笑顔が一番大切な日なのに。リヴァイさんのお誕生日はクリスマスと同じ日だから、みんなが特別になっちゃうんだ。一番に特別なはずのリヴァイさんが、特別じゃなくなっちゃうんだ。
リヴァイが嗚咽の中、途切れ途切れに聞いたことは、つまるところこういうことだった。
「……オレ、クリスマスなんてきらいだ。もうやらない」
最後にぽつりとエレンが言ったので、リヴァイは慌てて「そんなこと言うな」と返したが、内心では驚いていた。エレンが言ったことは、幼い頃リヴァイ自身が密かに心痛めたことだったからだ。クリスマスと誕生日を一緒にされてしまうのは損をしている気がしたし、自分が主役でいいはずの日に特別扱いをされないことは、やっぱり寂しかった。もちろん、大人になった今では、そんなことを考えていたことすら忘れていたのだが。
「エレン、ありがとうな」
泣き疲れ、真っ赤な目をごしごしと擦っているエレンの頬をやさしく撫でる。涙で濡れてひんやりと冷たかった。
「お前がそう考えてくれたことが、俺は嬉しい。それだけで十分だ。クリスマスのお祝いと一緒に、おめでとうと言ってくれたらそれでいい。だから、来年もクリスマスは楽しめ」
エレンは聞きながらゆっくりと頷いていたが、最後の部分で頑として言い放った。
「12月25日はリヴァイさんの誕生日だから。オレはもう、クリスマスはやらない」
変なところで妙に頑ななのだ。リヴァイは苦笑する。
「わかった。それなら、今後は24日にクリスマス会をすればいいだろう。俺の誕生日は25日だから、それで問題ないはずだ」
エレンはすこし考えて、妥協したようにむすりと頷いた。その姿を見てリヴァイはほっと胸を撫で下ろしたが、エレンはこの年から10年以上に渡り、しつこくクリスマスを嫌い続けたのだった。クリスマスじゃない、リヴァイさんの誕生日だ、と言って。
エレンが6歳のクリスマスのことを思い出したのは、クローゼットの奥に頭を突っ込み、クリスマスツリーのオーナメントを仕舞い込んだ段ボールを探していた時のことだった。引っ越しをしてもそのまま開封していなかった、子どもの頃の思い出の品を詰めた段ボールの中に、当時リヴァイにもらった手袋が入っていたのだ。子どもがつけるにしてはシックなデザインのそれを、「かっこいい」と喜んで大切に身につけていたことを思い出す。
あれからすこし年齢を重ね、小学校の高学年になった頃には、「カルラさんが寂しがるだろう」とリヴァイに説得され、クリスマスツリーを飾るようになった。オレはクリスマスを祝うんじゃない、リヴァイさんの誕生日を祝いたいんだ、と頑として言うと、リヴァイが言ったのだ。「俺の誕生日でもクリスマスでも何でもいい、俺は俺の周りの人たちがみんな楽しそうでいてくれたら、それが一番嬉しい」と。
「カルラさんたちが思い切りクリスマスが祝えないのは悲しい。お前がサンタを睨みつけるようにするのもな」
リヴァイはそう言って笑った。しょんぼりとうなだれると、リヴァイはやさしくその頭を撫でて続けた。
「でも、お前の気持ちは本当に嬉しい。……本当は、お前の言うようなことを、俺も考えていたんだ。ガキの頃。損してる気がするってな」
それからは、クリスマスへの憎しみを心に秘めるようにしたのだ。リヴァイさんを悲しませたくはない。メリークリスマスでも何でも言ってやろう。でも、オレだけは絶対に、リヴァイさんだけを特別扱いする。オレの一番大好きな人の生まれた、何よりも大切な日だ。
見つけた段ボールからオーナメントを取り出しながら、今年はどうやってリヴァイを祝おうかとエレンは考える。あの時抱いた気持ちは今も変わらない。リヴァイは覚えているだろうか。